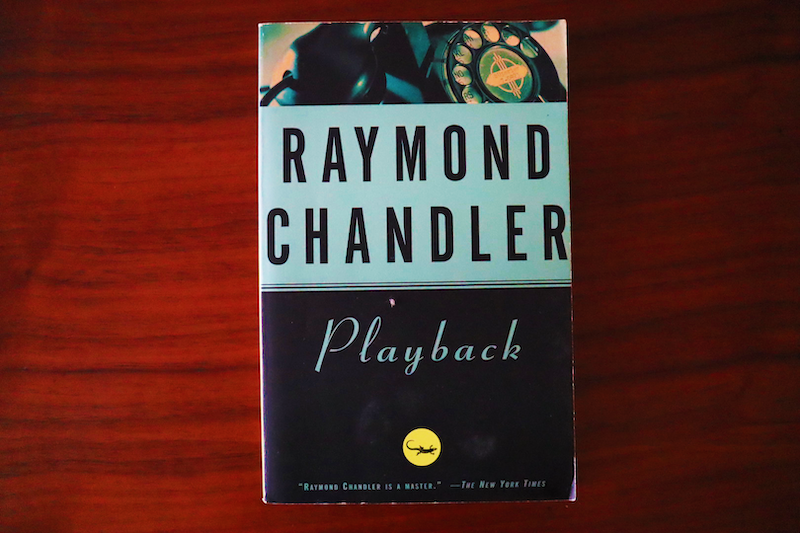今年の春。名曲喫茶支度をしながら、ドビュッシーを聴いていた。いつものように。
ピアニストはアレクシス・ワイセンベルク。このアルバムは僕にとってかなり、けっこう特別だ。
相当回数聴いているだけではなく、何よりも、何よりも、何よりも、あ、3回言っちゃった——数多の思い出や経験と直截に結びついている。
ドビュッシーのピアノ曲はサンソン・フランソワ、アントニオ・ミケランジェリ、ワルター・ギーゼキング他偉人たちの残した名盤も言うまでもなく個々に素晴らしいけれど、もしも、神様(あるいは神様ヤクザ)に「おい、兄ちゃん、ドビュッシーのピアノで1枚選べや」と凄まれたら、臆することなくこの盤を選んでしまいそうな気がする。
そういえば数年前、このアルバムのレビューを書いて投稿したことを思い出し、さっき久しぶりに読み返してみた。以下、抜粋(原文ママ)。
何百回聴いたかわからないくらい聴いている。
ドビュッシーの曲群に内在している「陽のイデア」(なるもの)を余すところなく表出すること、それのみを心に置いたような選曲と録音。そして演奏は一本気で、清々しく、力強い。ささくれだった心をいつでも「ぴん」とまっすぐに伸ばしてくれる。
ストレートな解釈、生硬なタッチはこの演奏より遡ること約30年前の名盤、ヴァルター・ギーゼキングのものにもっとも近いように思う。ロマンチストの酔っ払いが夢見心地に弾いているようなサンソン・フランソワの演奏とはいかにも対照的な、素面/明晰/実直な「独逸賢人」といった印象。
しかし、同時に白昼夢的きらびやかさもたっぷりと内包しているのが素晴らしい。ドビュッシーのピアノ作品集で1枚、と言われたら、迷うことなく、これを選ぶ。これまでも、これからも。(整体的ドビュッシー)
このやたら意気込んだレビューを記してから数年経ち、改めて今聴いてみても、このアルバムに対する印象は変わらない、全く。
このアルバムにおけるワイセンベルクの実直かつ剛健な演奏は完璧すぎる。
1曲目「塔」から、完全に心を持っていかれてしまい、ラスト「レントより遅く」に至るまで、一瞬たりとも緩む瞬間はない。「ベルガマスク組曲」も「子供の領分」も「喜びの島」も、全てが明晰な白昼夢の如く、宵闇に浮かび上がる星々の如くきらっきらに輝いてゐる。
十代の頃、フランスの小粋なピアニスト、フランソワ・ジョエル・ティオリエの弾くドビュッシーの「月の光」を聴き、それから数年後にこのアルバムに巡りあったように記憶しているのだが、それから各地の名曲喫茶で、買い求めたレコードでたくさんのピアニストの奏でるドビュッシーを聴いてからというものの、クロード・ドビュッシーという作曲家の怖さ、幽玄さをひたひたと思い識ることとなった。
ご存知、キャッチーかつ牧歌的な「亜麻色の髪の乙女」でさえ、たとえばミケランジェリが弾いたなら、それはまったく「別もの」になる。それは言ってみれば此の世と彼の世の中間地点(Limbo)の響きだ。しかし、そこにこそ、きっとドビュッシーの本質的な何かが宿っているのだろう、とも思う。もしあなたがミケランジェリの弾く「前奏曲」を通して聴いたなら、きっとドビュッシーという作曲家に対する印象ががらりと変わってしまうことだろう。それは底知れぬ井戸のように深く、虚無の1歩手前の空間の様に、此の世に具現化される直前の微妙なる息吹を感じさせ、叶わぬ恋に落ちた幽霊の如く儚く、美しく、やるせなく、いぎたない。
だけどワイセンベルクの演奏には、そのようなドビュッシーの底知れなさ、哀しみ、眠りみたいなものは——少なくとも僕には——微塵も感じられない。「微塵も感じられない」ことがこの盤の存在をひときわに際立たせているように思う。
ワイセンベルクの演奏から感じるのは、7月の草原に輝く朝露のような瑞々しい輝きと、草いきれのような鮮烈な清々しさと澄みきったひたむきさだ。それは太古の罪や穢れ(のようなもの)からどこまでもどこまでも遠ざかっていて、どこまでもどこまでもきらびやかな色彩を帯び(もし、あなたがモノクロで描かれた古き良きラブストーリーのような「永遠の煌めき」を求めるなら、ワルター・ギーゼキングのアルバムを聴いて頂きたい)、どこまでもどこまでも果てしなく損なわれ、同時にめくるめく生成をどこまでもどこまでも繰り返していく。ここ現象世界のように。
アレクシス・ワイセンベルクの奏でるドビュッシーは僕をいつでも「今、この瞬間」に引き戻してくれる。同時に、あの川面の永遠の輝きを思い出させてくれる。これまでも、これからもそうなのだ。