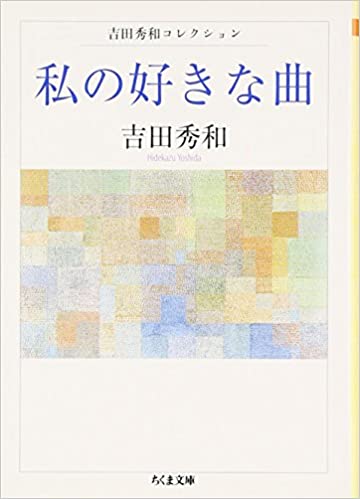
1 グールド『ゴールドベルク変奏曲』との出会い
クラシック音楽は幼少期の頃から聴いていた。
モーツァルト『交響曲第40番』の幼な心を激しく突き動かすような音像、ベートーヴェン『交響曲第6番』を聴いた時、感情全体を包みこむ巨大な揺りかごにすっぽり入って、大きく揺らされた時のような、あの決定的な感覚を今でもはっきり思い出すことができる。
でも、自分が自意識、もっと言えば批評的な意識を以てクラシックに触れるようになったのは、28歳の時、カナダはトロント生まれのピアニスト、グレン・グールドのデビュー盤『ゴールドベルク変奏曲』(1955年録音)を聴いた時だった。

それまで聴いてきたピアノとは、また、バッハの音楽とは、明らかに「何か違う」と感じた。
でも、どのように違うのか言語化することができなかった。そのことに、違和感とある種の苛立ちを覚えた自分は、晩年にグールドが録音した、傑作の誉れ高い『ゴールドベルク変奏曲』(1981年録音)を聴くことを踏み止まった。
デビュー盤を相当回数聴かないことには、この盤を理解することはできないだろうという気がした。言い方を変えれば、55年の盤には「よく聴かないと汲み取れない何かがあるぞ」と自分の内の誰かがきっぱりと命じていたのだった。
その声に従って、毎日のように55年録音の『ゴールドベルク変奏曲』を聴いた。
中古レコードも購入し、店仕事に入る日は店のレコードプレイヤーで。外出する日はCDウォークマンで。車の中ではダビングしたカセットテープで(とてつもなく古い中古車で、テープしか聴けなかったから)。
そうやってあらゆる場所で、あらゆる形態で聴くことを日課のようにしているうちに、バッハの音楽が、グールドの打鍵が自分の体に染み込んでいくような心地がした。ゆっくりと、でもじわじわと確実に。

2 音楽を言葉にする
102日めか103日めだったと思う。それまでの51年版の代わりに、前もって国分寺の新星堂で買っておいた81年録音『ゴールドベルク変奏曲』のCDの封を開け、聴いた。
その音が鳴った時の、まるで強く殴られて、突然視界がクリアになるような衝撃をよく憶えている。
最初の数回は、ただただ夢見心地で聴いていた。そして、「いったい、これは」と思った。
同曲の2枚は「何か」が明らかに異なっていた(そして通底していた)が、その時の僕の内にはふたつの盤の違いと衝撃を語るための言葉を持ち合わせていなかった。
それからグールドのブラームスを聴き、モーツァルトを聴き、シェーンベルクを聴き、平均率クラヴィーアを聴いた。
図書館でレンタルしたり、クラシックに詳しい伯父から借りたりして、当時聴けるものは1年かけてひと通り聴いたように思う。
グールドの演奏には、僕がこれまで聴いてきた音楽を、それまでのクラシック観を一新するようなインパクトがあった。
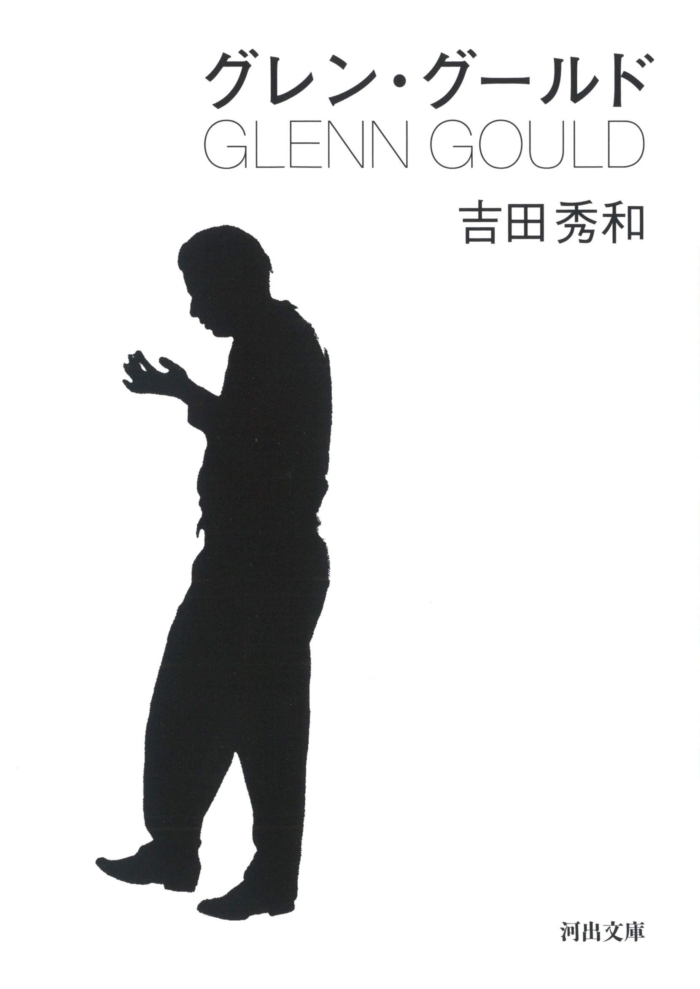
僕はまず、グレン・グールドのピアノの謎の魅力を掴みたいと思い、吉田秀和の本を手当たり次第に読み始めた。
クラシックに造詣が深いわけでも、楽譜が読めるわけでもない僕には読んでも意味のわからない箇所がたくさんあった。
でも、そこには、たしかに「理解できる言葉」があると感じた。初めて「話が通じる人」に出会ったような喜びを伴って。
グールドの言葉にならない凄さを、どうにかして言葉にして他者に伝えようという瑞々しくも強固な意志がひしひし感じられた。
吉田秀和の書き方、感じ方、考え方は、他のどんな評論家ともエッセイストとも異なっているように思われた。理知的であり、私的であり、詩的であると同時に、万人にとって普遍的な「何か」を掴みとる力強さ。
3「私の好きな」とは
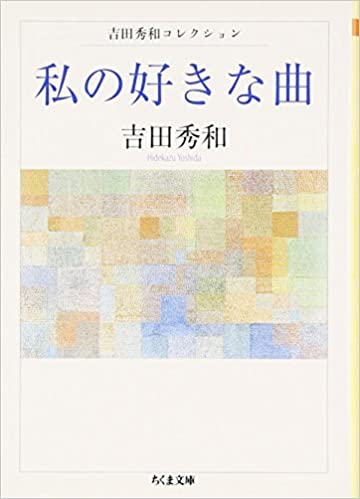
本書『私の好きな曲』は、たしか3冊めか4冊め——集中的に、系統的にクラシックを聴くようになって4、5年経った頃に読んだと記憶している。
氏が「好きな」曲を挙げて、それについてけっこうな枚数で書かれた本。選ばれた楽曲は見事にバラバラだし、「好きな曲」という以外の共通項はおそらくほとんどない。
しかし、僕はこの本から、音楽のみならず、自分の「好き(something you love)」について語る総合的な姿勢・視点を学んだ。
「好き」とはどういうことなのか? 或る対象を見聴きし、書く——すなわち「批評する」とは——どういうことなのか? そのほとんど全てを。
「私の好きな」とは、眺望的な、歴史的な視座に立って書くことではない。端的に言えば、全てを「私」に由って書くということである。しかし、そこで言う「私」とは、けっしてこの個人的な「私」だけを示さない。
そこでは、それを好きな私とは何か?という抜本的な自問が生まれる。その「私」には、「私の前」と「私の後」を見据える歴史的な視点や、私を相対化する眺望的な視座も否応なしに含まれる。
4「私」と「詩」
氏の存在と功績は「音楽批評」というジャンルにおいて、あまりに著名であり、偉大であり、もはや「古典」のポジションを獲得していると言って良いだろう。しかし氏の批評の一部は、やはり一部のクラシック・ファンにとってはかなり不愉快なものであるらしい。
何故か。それはこの「私」への誤解に因るものではないかと思う。
吉田秀和は原典至上主義ではない。作曲家こそが神であるといったスタンスを徹頭徹尾取らない。
作曲家に対しても、演奏家に対しても、聴衆に対しても、その目線は公正であり、芸術とそれを享受する者を腑分けしない。
そこにあるのは「私」への愛と信頼であり、同時に懐疑であろう。そして、くどいようだが、その「私」は必ずしも吉田秀和その人だけを示さない。私は、深い内省と省察——そしてたゆみない勤勉な研究において——ようやく普遍的であり批評的な「私」に到達することができる(できないこともあるが)。
もうひとつ。氏の文章には「詩」の要素、いや、詩そのものがある。
僕は詩が宿らない批評を——いささか誤解を招く言い方かもしれないけど——信用することができない。優れた批評とは、全て私的であり、詩的であるというのが僕が個人的に掲げたい標榜だ。
吉田氏の、ときに詩的で、文学的な文章を批評たらしめているのは彼の強靭な文体に因るだろう。その意味では、同時代の書き手、小林秀雄と彼の類似点(と相違)を見逃すことはできない。彼もまた、強靭な文体と自身の内なるダイモンに突き動かされて文章を書いている評論家であり、詩人である。しかし、詩には「誤解」がつきものでもある。

中原中也(中也は小林秀雄の友人であり、吉田秀和の先輩的存在だった)に対し、吉田秀和はその印象と思いでについて、随筆集『ソロモンの歌』で書いている。
私は、いつか文字通り、雨戸の隙を洩れて入ってくる陽の光が天井にうつる影をみながら、彼の声をきいていたこともある。(中略)
天井にゆれている光をみながら彼の歌をきいていると、私には、小鳥と空、森の香りと走ってゆく風が、自分の心の中でも、一つにとけあってゆくのを感じた。そうして、この倦んじた心、手にてなす何ごとも知らない心。
吉田は中原の詩に音楽を聴く。彼のエピソード、人間性よりも、彼が時おり口ずさんだ鼻歌の方が中原の存在の本質を顕していたかの如く記しているのは象徴的だ。
そしてアントン・ブルックナーに関する記述。
では、ブルックナーの何がそんなに良いのか?
音楽のクライマックスが、その緊張の絶頂であると同時に、大きな、底知れないほど深い解決のやすらぎでもあるということ。その点で、まず、彼は比類のない音楽を書いた——と私は考える。
あまりに短い文章だが、まさに適切な考察であり、詩である。
しかしながら、氏の著書には(僭越ながら)「いくらなんでもそれは……」と感じるような評も(まれに)ある。
独断、偏見と見なしたくなる時も多い。一部のクラシック・ファンが反旗を翻すのもよくわかる。
僕も自分が大好きなドイツの作曲家、マックス・レーガーのことを、「私は、この人のことはよく知らないが、略しても良いだろう。」(名曲100選)と書いてあるのを読んだ時には、さすがに本を放り投げそうになった。
氏の真骨頂は短文のものより、氏が選んだ作曲家/演奏家について1冊たっぷり書いた長めの批評文にあるように思う。
個人的には、本書『私の好きな音楽』『グレン・グールド』『バッハ』『音楽の旅・絵の旅』を読み返すことが多い。
(とくにクラシック音楽にそこまで興味のない方には、『音楽の旅・絵の旅』は良質な紀行文とエッセイで構成されているので、とてもお薦めです)
批評に対して、客観性、眺望的な視点、厳密性を求める人には、吉田秀和の本はあまり気に入らないかもしれない。
でも自分のように、「私の好きな」という視点を深め、座標軸にしたいと考えている人には、氏の本をぜひ開いてみてほしい。
「クラシック音楽」という対象に留まらず、生きている上で、「何か」を言葉にする上で、恐ろしく大切な姿勢が含まれている、というより、全てがその姿勢の体現であり、発露そのものだったと思うのだ。吉田秀和という人の魂は。

5 最後に
ここまで、自分の好きな本について、僭越ながらしたためてきました。
その選択の幅の狭さ(あるいはバランスの悪さ)はさて置き、10冊全てが自分にとって大切な思い出、自分の人格や趣味嗜好を形成してきたと言いきれる本です。
僕など及びもつかない読書家の方から見たら、「浅いな」と思われるかもしれません。「いかにもだね」と思われるかもしれません。「これ入ってて、あれが入らないのは変」「まあ、好きってのは人それぞれだからね」と思われるかもしれません。
それに対して——開き直るわけではないのですが——言い返す言葉は、今のところ何もなさそうです。
ただ、僕にとって、何よりも大切なことは、自分が「本当に」好きな本は何なのかとにかく選んでみること。そしてこれらの本たちが「なぜ」「何が」「どのように」好きなのかを、自分の内で熟成させてみることでした。
そうして「好きな本」を文章にしてみることによって、初めてそれらの本が自分にとって「何」であった(なかった)のか、少しでも掴みたかった。
その試みがうまくいったのかどうかはわかりません。かなり稚拙なものになってしまったかもしれない。でも、とにかく選んで、書いてみることに意味があったのです。
そして、このような観点——好きな本や音楽などが自分を形成したという見方、語り方、向き合い方を、僕は吉田秀和氏の本から——かなり根幹の部分において——教わったと(勝手に)思っています。
本稿「私の好きな本」というタイトルは——もはや言うまでもないことかもしれませんが——本書『私の好きな曲』から拝借しました。
『私の好きな本』をここまで読んでくださり、ありがとうございました。
ここで紹介させて頂いた本が、書いてきた文章が、何かしら皆さまにとってお役に立てれば、心から嬉しく思います。(了)堀内愛月








