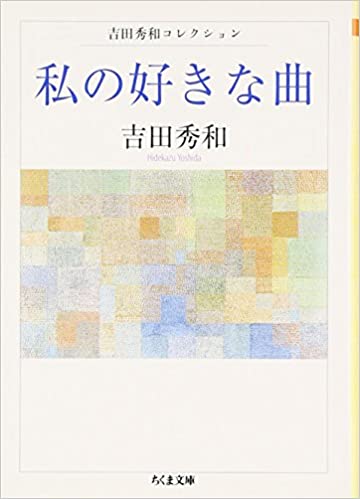「わしにとって世界が不気味なのは、それがすばらしく、荘厳で、神秘的で、底の知れないものだからだ」(『呪師に成る』より)
なぜ、人は「本」を必要とするのだろう。
なぜ、人は熱心に本を読み、情理を尽くして好きな本のことを語りたがるのだろう。
まるでそれだけが、自分をこの世界に存在させてくれると固く信じているかのように。
まるでその熱量が、自分をこの現実世界にくっつけてくれる「ニカワ」であるかのように。
かく言う自分も、ここまで熱心に「好きな本」のことを、自分なりの熱情と愛情を携えて何やかやとしたためてきた。
自分の好きな本について書くことは、思っていたより大変な作業だけど、書きながら、どこかで安堵している自分がいた。
そうだったそうだった、僕はこういう本が好きな、こういう人間だったよな、と。
そう、好きな本や出会った人々が「自分」という人間を構成したとしか思えない時がたしかにある。
それらが存在しなかったら、僕など(ほぼ)無であるような。
言うなれば、昆布を入れっぱなしにした乳白色の出汁のようなものだ。
そこに具材が入って、よく煮立てて、ようやく何らかの「鍋」ができあがる。
そうして、これこれこういう具材が入った、こういう味の鍋なんです。
などと、自分という鍋の有り様をどうにか表明することができる(どうして鍋に喩えているのか自分でもよくわからないけど…)。

本書「呪術師」シリーズを「好きな本」として挙げることをずいぶん迷った。
この本は「自分を構成した」と思いこんできた諸々を「チャラ」にしてしまいかねない危険な本だから。
自分が本当は何者でもないこと、「空」であることを暴き立ててしまう類いの本だから。
どんな本なのか?
説明するのはきわめて難しい。ドキュメンタリー風でもあり、ルポタージュ風でもあり、オカルト本であり、対話集であり、幻想小説であり、マジック・リアリズム文学でもあり……そのどれでもあり、どれにも当たらない。
文化人類学者を志すカルロス・カスタネダという学生が、メキシコの僻地でドン・ファンというインディアンと出会い、植物学を学ぶために彼の弟子となり、彼との対話やドラッグ体験、メキシコの自然の中で途方もない出来事の中、「呪術師」にジョブ・チェンジし、成長していく……
いや、そんな風に要約しても意味はあるまい。

僕は本書の語り手、カルロス・カスタネダに自分の「管理された愚かさ」を見た。自分の世界に必死にしがみついてきた自分を見た。
カスタネダは、自分がこれまで得てきた知識と経験と嗜好を後生大事に抱え、まるでそれだけが世界であるかのように考え、振る舞ってきた。
他者や、自分が所属していない世界に対して一応の理解を示しながらも、内面には右も左もわからない傷ついた赤ん坊が心許なさそうに突っ立っていた。
彼は、そんな自分に対して長いこと苛立っていた。自分が儚くてちっぽけで、ろくすっぽ「見えて」いない、ただ世界を眺めているだけの弱くて虚ろな存在にすぎない――心の何処かでずっとそんな風に感じてきたのだった。
タロットカード『カップの4』の、いかにも物足りなさそうな青年のように。

しかし、たまたま友人と訪れたアリゾナ州のバス停で、或る老インディアンと出会った瞬間、カスタネダの世界は一変する。
ロスでの穏やかで便利な暮らしを捨てて、彼(ドン・ファンと名乗るヤキ・インディアン)とメキシコの山奥でプリミティブな生活を過ごしているうちに、それまで自分が自分とみなしていたものが「真の自分」とは一切合切無関係であることに気づきはじめる。
彼がこれまでしがみついていた世界は音を立てて(あるいは無音で)揺らぐ。
「お前の履歴を捨てて、世界を止めろ」
ドンファンはそう言う。長い抵抗と逡巡の後、必死にしがみついていたものを彼はすっかり手放す。儀式を行う。煙を喫う。世界は消える。
代わりに浮かび上がってくるのは、彼がこれまでその存在を垣間みたこともなかった、新しい世界だ。
それは幻覚や夢ではない。「呪術師の世界」と呼ばれる。
彼はそこで呪術師としての修業経験をどうにかノートに書き留め、ルポタージュ風の本に仕上げることを試みる。
「書くこと」は理性と常識を揺さぶられる中で、カスタネダが唯一しがみつける場所であるから。
カスタネダはドンファンと過ごした1年と、彼から学んだ教えを1冊の本に記した。
その本は『呪術師と私』というタイトルで出版され、ベストセラーとなる。
若きカスタネダはドンファンの教えと「あちらの世界」での奇想天外な体験を記したことによって、「こちらの世界」で大きな名声を得たのだった。

出版から1年後、カスタネダはその本を手みやげに、再びドン・ファンの元に赴く。
「これはあんたのことを書いた本だよ」
『呪術師と私』を一読し、ドンファンは、大笑いする。「お前は何もわかっていないことがよくわかった」
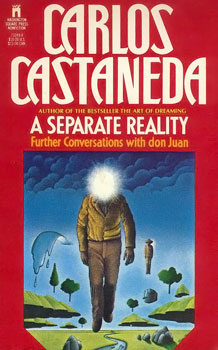
2度めの帰依
2作めである『呪術の体験』は、本を書き上げたカスタネダが数年ぶりにドン・ファンと過ごし、新しい世界を探求することを決意することから始まる。
彼は再びドン・ファンの弟子となる覚悟を決めた。カスタネダの新しい旅が始まる。
それから展開する10冊は、ドン・ファンの教えを必死に書き留めることによって出来上がった処女作とは全く異なる。
もはや観察者ではなくなった、新しい世界に足を踏み入れた見習い呪術師の、魅力と危険と輝きにみちた世界を描いた一大絵巻である。
一読して、「トンデモ本」と感じる方も多いかもしれない。
実際、アメリカにおいても、「カスタネダの書く本は研究でもノンフィクションでもルポタージュでもなく、荒唐無稽な作り話に過ぎない」といった批判も飛び交っていたようだ。
かの『TIME』 誌(73年)では、カスタネダを特集しながらも、彼の著述・履歴の大部分が嘘であることを暴こうとし、カスタネダ批判が殺到した(昨今言われるところの「炎上」である)。

対する擁護派は、「もしウソっぱちでもこれだけ面白いんだから良いんじゃね?」といった読者や、「文化人類学・植物学におけるきわめて貴重な達成である」といった高名な学者にまで及んだ。
とにかく、カスタネダの著作はどんどん話題になり、売れに売れた。
しかし、その後カスタネダは隠遁し、メキシコでの自分の体験とドン・ファンについて、自分の妻にさえ沈黙を保った。結局、真相を1人で墓に持っていってしまったのだった。
「物語」とは?
本書は全部で12冊刊行されたが、未読の方には初期3冊『呪術師と私』『呪術の彼方へ』、そして本書『呪術師に成る』を強くおすすめしたい。
出版から四半世紀が経って、本書にたまたま触れた僕は、本書を「最高に面白い幻想奇譚集」と感じた。
当時、いつでも手元に置いていたくて、旅行にも仕事場にも肌身離さず持ち運び、あらゆる場所で読み耽った。
どうして自分は本書にそこまでのめり込んだのだろう?

「物語」を読む時、「それ」は確かに実在するのだが、どこかで「これは物語に過ぎない」という視点が共存している読者は多いだろう。
フィクションはあくまでフィクションである(虚構、とまでは言わないまでも)といった、折り合い的認識が何処かにつきまってしまうというか。
でも本書に関して、読者は「これはほんとうに起こったことかもしれないし、そうではないのかもしれない」といった認識のあわいを(避け難く)抱きながら読み進めていくことができる。
ここには、僕にとって理想的な「物語」がある。
本書は、スペクトラム(境界の曖昧さ)が、どれほど「物語」に強度と深みを与えるか、という実験小説でもあるようにも思える。
ドン・ファンなる呪術師インディアンは実在したかもしれないし、ほとんど全てカスタネダ氏の創作なのかもしれない。長い夢なのかもしれない。でも、それはもはや重要ではない。
本書を読んでいると、「実在する」とはどういう次元における定義なのか? そんな古典的かつ根本的命題を喉元につきつけられるように感じる。
そのくらい、本書で描かれるカスタネダの無垢な探求心と執拗な描写力、そしてドンファンの謎めいた有り様には、現実と夢を単純に二分することを凌駕する「分離したリアリティ」を伴うのだ。
フランスの哲学者ドゥルーズ=ガタリは、カスタネダの第5作『呪術の彼方へ』(1978)発売後、以下のように述べている。
「カスタネダの本を呼んでいくうちに、読者にはドン・ファンというインディアンの実在が疑わしくなり、他にも多くのことが疑わしくなる。
しかし、結局それは、まったくどうでもよいことだ。カスタネダの本が民俗誌学というよりは諸説の混沌とした記述であり、秘技伝授についての報告というより、様々な実験の記録であるとしても、むしろそれでいいのだ」

ここまでつらつらと記してきたが、自分にとって「世界」とはどうやら「本」であるらしい。
僕はカスタネダの一連の呪術師シリーズを読むことで、そのことがすっかり腑に落ちたように思う。
本こそが、文字通りのザ・ワールドであるようだ。
(その「本」とは、必ずしも紙に印字され、束ねられた本のことだけを意味するわけではない)
そして僕にとっての「呪術」とは、「タロット」のことであるようだ。(この話はまた近く、別の機会に…)