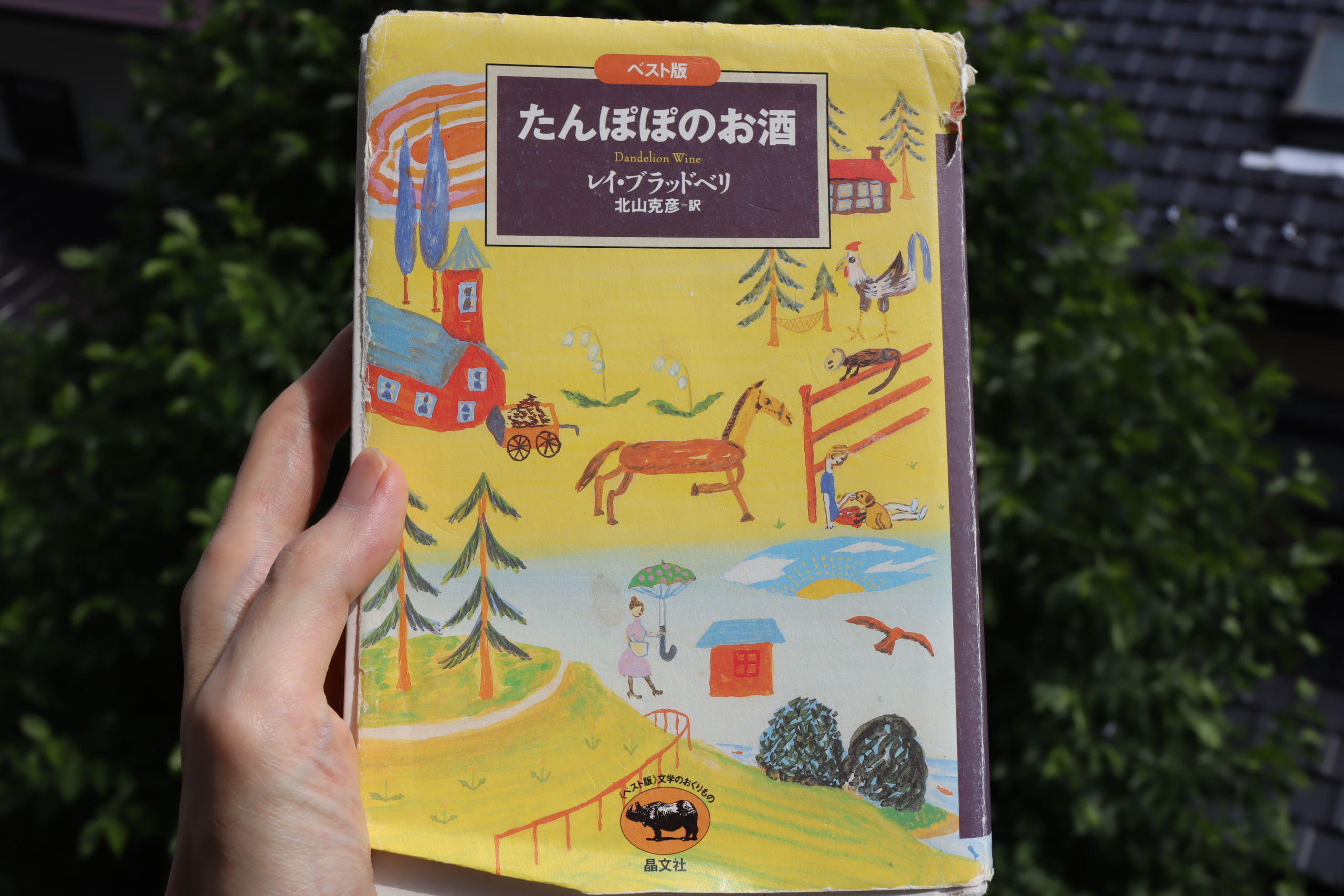ちょうど今くらいの時期の、阿佐ケ谷の午後16時。
「ここを先途」とばかりに蝉が勢いよく鳴き続け、
靴を履いていても熱が伝わってくる歩道にはホースの水が打たれ、
夏を謳歌するうら若き男女が
There is no time like the present.
青い字でプリントされたトートバッグを肩から下げて、
暑さをも愛おしむようにぶらぶら歩いている。
足早に彼らを追い越して、昔ながらの文具店や書店、ファンシーショップが並ぶ商店街を脇目も振らずに通り抜け、味のある書体で『珈琲雨水』と書かれた、筒箱形の看板が出ている雑居ビルの階段を息を切らせながら上がる。
ドアを押し開け、息を整え、軽い緊張感を押し殺しながら店内を一瞥する。
お客さんが2人。文庫本を読みながらプリンを口に運んでいる女学生と、壁際の席で絵を眺めている老人。
中間あたりの席に腰を下ろすと、注文を取りに来た店主に「9番、お願いします」と小声で言う。
僕よりだいぶ歳下で、ハンサムで(イケメンという言葉は使うまい)、物腰丁寧で、生真面目な表情で、
それだけじゃ言い尽くせない魅力をたたえた店主が、今日もぴしっと糊の効いた白いシャツを着て、姿勢良くコーヒーを点てている。
奥で電動ミルががりがりがりがりがり……。
そっと覗き見ると、ネルで丁寧に落としている店主の姿が見える。
スピーカーからはトム・ウエィツの『レイン・ドッグ』(たぶん)が小さな音で流れている。
やがて、小ぶりのカップに入ったコーヒーが供される。
その艶のある表面をしばらく見つめてから、ほんのひとくち口に含む。
粘度があって、ウイスキー樽のような独特の後味を後に残すとくべつなコーヒー。
それは、夏に飲むと夏の夜よりも夏の夜の味がする。
秋に飲むと秋の夜よりも秋の味がする(春と冬は言うまでもない)。
夏のとろりとした宵闇がそのまま飲みものになったような不思議なコーヒー。
あれは僕にとってとくべつだったように、きっと誰にとってもとくべつなコーヒーだった。
誰も、あの店の階段を上がって、あのコーヒーを口にすることはできない。少なくとも、今は。
そんなことを思いながら、熱い濃いコーヒーを1杯淹れて飲んだ。