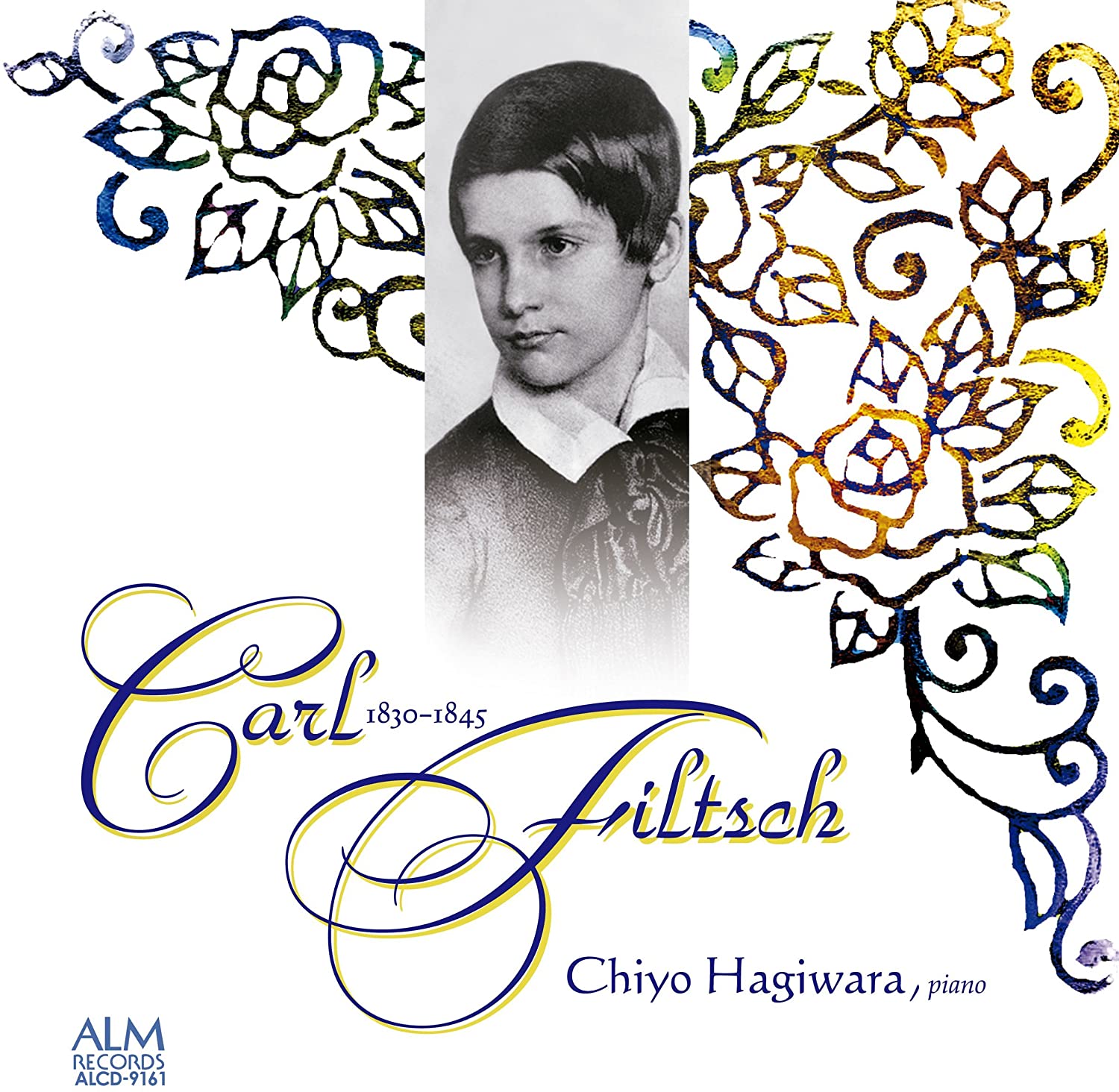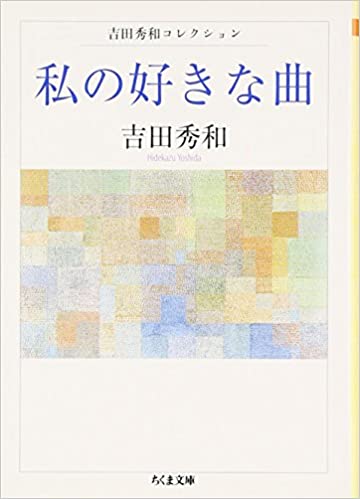もうずいぶん聴きなれた今でも、スリリングかつ融通無碍、かつチャーミングに感じるライブ演奏。
しかし、それだけには留まらない。何処か遠くて遥かな場所にぐいぐいと引っ張られていくようなサイケデリックかつ遠心的なるベートーヴェン演奏。
それがたった今、終わった。羨望と戸惑い混じり(たぶん)のばらけた拍手が室内に響き渡る……。
あ〃、30分だけでいいから、1935年にこの場所(コペンハーゲンのラジオ局)に居合せた聴衆になってみたい。そしたらこの両耳で生のステレオ演奏が聴けるのに。などと考えていると、ブラームスのヴァイオリン・ソナタが始まる。思わず居住まいを正す。
今日の自分は、いささか参っているらしい。或る意味、私は常に参っているし、或る意味では常に元気溌剌なのだが、今はこのアドルフ・ブッシュのぐにゃぐにゃヴァイオリン演奏(褒めています)に持っていかれ、自分もろとも得体の知れぬ場所に今にも持っていかれそうである。
しかし、ルドルフ・ゼルキンの闊達なピアノがそれを引き止めてくれる。ゼルキンのピアノは明晰さそのものであり、無体なブッシュの演奏を強靭な車軸となって支え、同時に星を映す暗い空のように引き立てるピアノだ。ブッシュ/ゼルキンは「義親子」の関係であったが(ゼルキンの妻はブッシュの娘イレーネさんであり、その息子はご存知現役ピアニストのピーター・ゼルキン氏。息子ピーター氏が壮年期に録った「ゴールドベルク変奏曲」はたいへん素晴らしい)、関係性とは無関係に、その音楽的気質・スタンスはずいぶん異なっているように思う。
ブッシュ氏はヘタウマで(私見です)、天才で、夢想的で、「たが」が外れかけている。
ゼルキン氏は明晰で、堅実で、朴訥としている。が、実はブッシュに負けず劣らず夢想的である。
ゆえに2人の演奏はどうしたって「夢」の領域に踏み込まざるを得ない。おいおい、そっちに行ってしまうんか…それも致し方なし。だから、聴いているとどこまでも眠たくなってしまう。ああ、このままベッドに倒れ込もう。
或る音楽を聴くことと、その音楽について何か記すことは(言うまでもないことだが)全く違った行為である。
それはよく言われるように、「音楽を言葉にするのは難しい(あるいは不可能である)」とは、少しばかり違った意味で。
例えば、糖雨が静かに降りしきる夜更け。
人気のない公園の楓の樹の下で、雨の中、息を潜めて聴いていたブラームスが、片手でさしていた深緑色の傘の柄に貼られたセロファンの手触りとか、ダッフルコートのポケットに入れていたポータブルCDプレイヤー(単3電池2本で可動)の重たさとか、水気を帯びた5月のなまぬるい空気とか、そういったもの全てが——
真っ直ぐに疾走したり、雅に重なり合うフレーズと混じり合って、ほとんどひとつになって、「ああ、もしこれを後から思い出したり、書きつけてみても、今感じてること、今聴いている音、今ここにいる不思議を1ミリたりとも表しちゃくれない……」
言葉はいつでも音楽に遅れをとってしまう。こうして自分にとってとくべつな曲を公開し、ここに所感やら、トリビアめいたことをしたためてみても、あの時流れていた音、吸いこんでいた空気、あの手触りに比べたら……いや、比べることさえできやしない。
もっともらしいことを書こうと思えば、少しは書けるだろう。が、7曲ぶんのライナーノーツ(風長文)を続けてしたためているうちに、もっともらしいことを書くことにいささか飽いてしまったようだ。
この曲がヴァイオリン・ソナタにしては珍しく4楽章構成だということも、かつて自分がブラームスが大の苦手だったことも、『ヴァイオリン・ソナタ』第3番は他2曲のヴァイオリン・ソナタに比べても「暗く、重たい」と評されており、それはこの時期にブラームスが友を亡くし、恋に破れ、人生の苦みを痛感し始めた時期である故と推測されたことも、1番/2番の溌剌さは影を潜めているものの、四季ごとに採れるたわわな果実のような芳醇と苦味にみちていることも、そういう話は(さっきまで頑張ってしたためていたのだけど……)なんだか急にどうでもよくなってしまった。
そういうわけで、申し訳ないのですが、最後に個人的な思い出をひとつだけ。
かつて、此のヴァイオリン・ソナタ第3番を文字通りの「子守歌」にしていた時期がある。
当時、机の上に並べて置いていた古いスピーカーからアドルフ・ブッシュとルドルフ・ゼルキンが奏でたこの曲をかけると、当時同居していた白猫がそれが「おやすみ」の合図であるかのように、僕が横たわっているベッドの上にのそのそと這い上がってきて、「どすん」と胸の上に乗っかった。
暗闇の中で、人と猫の耳をじっと傾け、私たちはこの曲を聴きながら、(おそらく)ほぼ同時にやってきたまどろみの中に身を任せ、暗い眠りの底へと沈んでいった……。