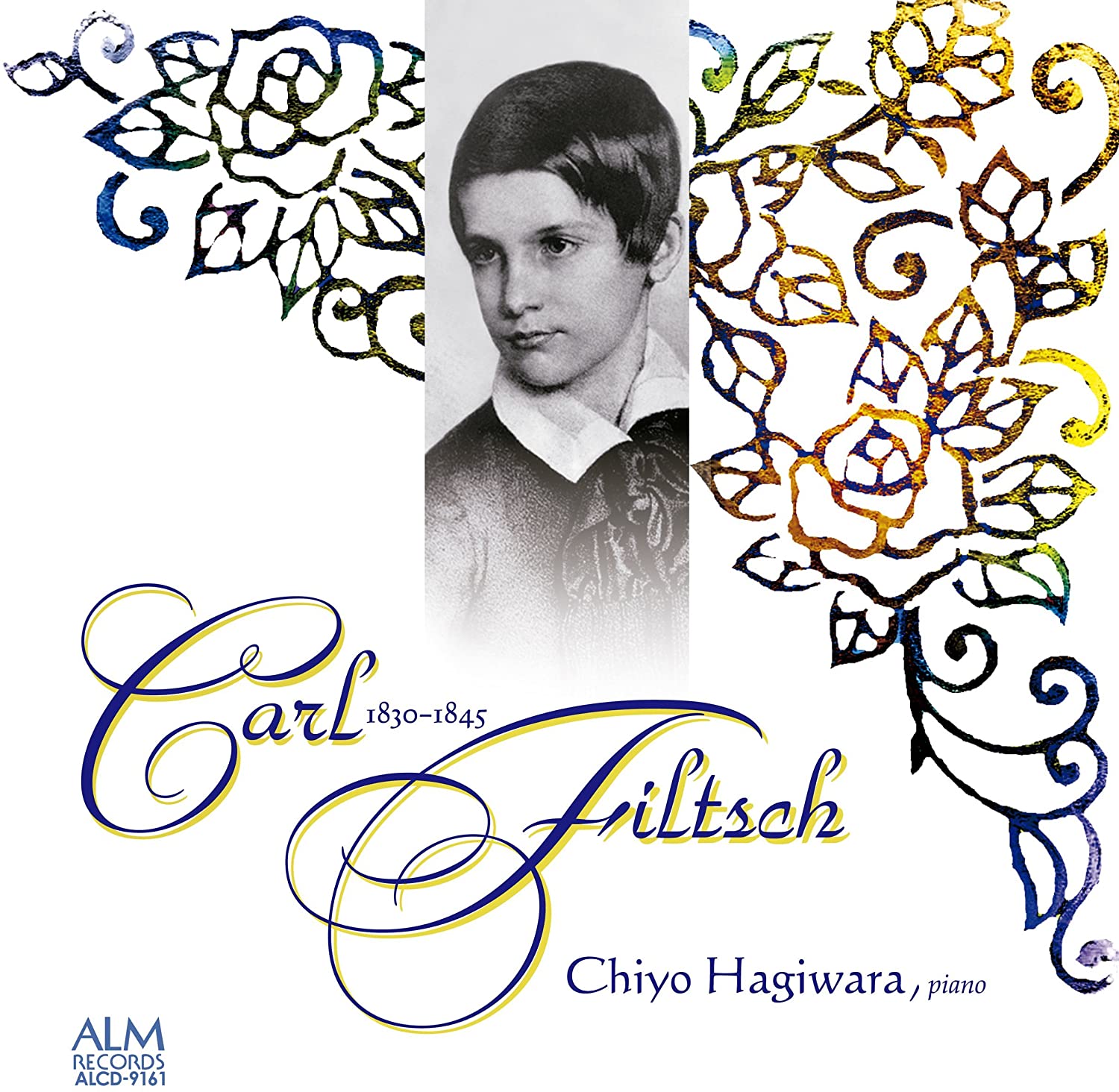今日は拙プレイリスト「Tsuki-Kusa-Record」4曲め、モーツァルトのピアノ・ソナタより「第12番 2楽章(アダージョ)」について書かせて頂きます。
アインシュタイン氏とゲーテ氏、かく語りき
このピアノ・ソナタ第12番がモーツァルトのキャリア史上、どういった成果に位置づけられているのか寡聞にして知らないのですが、あるいはモーツァルトのピアノ・ソナタ18曲の中でも「隠れた名曲」的存在なのかもしれません。
とくに2楽章は、モーツァルトの匠の芸「コロラトゥーラ」、というのは比較的早いフレーズの中に装飾を施された華やかな音節の呼称なのですが——このご時世、「コロ」という接頭語が出てくるだけで何だかやるせなさを禁じ得ません。
話が逸れました。
ご存知天才物理学者アルベルト・アインシュタイン氏は、稀代のモーツァルト研究家としてもよく知られています。や、研究家というよりは「大ファン」という方が近いかも。
何しろ、インタビューで記者がアインシュタイン氏に、「あなたにとって死とは?」と尋ねたところ、「死とはモーツァルトを聴けなくなることだ」と答えているほどですから。
そんなアインシュタイン氏はこのピアノ・ソナタ12番を「モーツァルトのピアノ・ソナタでもっとも目立たない曲」と評したらしいのですが、さらに続けて述べています(ピアノ・ソナタ第12番について述べられたもので、これ以上素晴らしい言説はないと信じているので、少々長いのですが、氏の発言を引用します)。
このソナタの開始の魅力は、それが開始ではなく、第2楽章のように叙情詩的で歌に満ち、まるで空から落ちてきたもののようであるという点に存する。 それにつづいて愛らしい自然の音響のような楽節後部が、左手のホルン五度を伴って現われ、それからはじめて、分析的な版本が「エピローグ」と呼ぶニ短調の緊迫がくる。 それは短調の緊張に満ち満ちているが、そのなかから第2主題が、まるでエアリエルのお伴のなかから出てくる光り輝く姿のように浮かび上る。 思いつきから思いつきが生じる。
『アインシュタイン』P202-203
「分析」というにはあまりに詩情溢れる表現ではありませんか。
「第2主題が、エアリエルのお供のなかから出てくる光り輝く姿のように浮かび上がる」というくだりがとくに素晴らしい。
「エアリエル」というのは、シェイクスピア『テンペスト』に現れる精霊、あるいはジョン・ミルトン『失楽園』に登場する堕天使、天王星の衛星の名でもあります(「アリエル」とも読まれます)。
「思いつきから思いつきが生じる」というのは、この曲に限らず、モーツァルトの超自然生成的旋律を聴いていると誰もが——とまでは言わずとも、多くの方が感じてられることでしょう。
この「善なる自然が与えてくれた(奏でてくれた)恩恵」という、心身を穏やかに巡っていく暖かな血の巡りのような音楽は、モーツァルトが創作した音楽作品に色濃く顕れているように思います。
もうひとつ、僕がモーツァルトを聴いていると勝手に想起するのは、かの文豪(という呼び名では収まりきらない偉人)ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテが『ファウスト第2部』に遺した1節です。
天のこう(「さんずい+景+頁」)気の薄明かに優しく会釈をしようとして、
命の脈が又新しく活発に打っている。
こら。下界。お前はゆうべも職を曠(むなしゅ)うしなかった。
そして今朝疲が直って、己の足の下で息をしている。
もう快楽を以て己を取り巻きはじめる。
断えず最高の存在へと志して、
力強い決心を働かせているなあ。(訳・堀辰雄)
僕にとって、このphraseは完全に「モーツァルトそのもの」を詩的に表現していると言っても過言ではありません(堀辰雄氏の対訳もまた見事ですが)。
「林檎の味」
アインシュタイン御大の言説とゲーテ殿の引用で、この曲に対して僕などが言うべきことはとっくになくなってしまったような気がしますが(僭越ながら)、もう少しだけ続けます。
モーツァルトのピアノ・ソナタでも僕はこの第12番が少なくとも全ソナタ中3本の指に入るほど好きで、とくにこの2楽章には、自分勝手な副題まで付けて、長く親しんできました。
そう書いた以上、(誰に尋ねられなくとも)そのタイトルを明かさぬわけにはいかないでしょう。
そのタイトルは「林檎の味」というものです。
どうして林檎の味なのかと言えば、この曲を初めて聴いた時から、曲に対する所感よりも林檎の味を先にはっきり味蕾に感じてしまったから。「味」は言葉で得た所感よりも自分の内に(生理的に)しつこく残り続けるらしく、以後この曲を聴くと甘く、苦く、酸っぱい林檎の味が常に変わらず立ち上がってきます。
(余談ですが、ずっと昔、モーツァルトに明るい知人にそれを話したら、「それはよくわかるような気がする」と言ってもらって、むやみに嬉しかったことが記憶に残っています。)
これを読んでくださっている方も、「そう言われると、林檎の味がするような……」と思って頂けるとやっぱり嬉しいです。まあ、梨でもスモモでも良いですが……それはこのピアノ・ソナタ第12番2楽章が、果実のイデアをも包摂するほど融通無碍な楽曲であることの証左となります。
グレン・グールドのモーツァルト演奏

そして当プレイリストにこの「林檎の味」を入れるにあたって、ピアニストについて、これまでの楽曲とは違って一切迷いませんでした。
どうやら、自分はこの楽曲に関しては、かねてよりグレン・グールド氏の演奏でしか聴けないようです。無論、モーツァルトのピアノ・ソナタの中にはウィルヘルム・バックハウス、リリー・クラウス、ワンダ・ランドフスカなどの、大家の演奏で大好きなものもたくさんありますが、こと12番に関しては、グールドの打鍵でしか心の深いところに入ってきません。や、「林檎の味がしない」と言うべきか。
その理由について、このライナーノーツを記すにあたってずっと考えていました。「グールド氏の演奏で初めて聴いたから」とか「グールド氏の演奏がとにかく素晴らしい」からといった理由でこの項を終わらせてしまっても良いのですが……。
頑張って少し突っ込んで考えてみると、無視できない理由のひとつに、グールド氏が他の演奏者とあまりに異なる(おそらくは原典を省略して弾いた)箇所が大きいように思います。
「こんなのがアリなのか?」と思わないこともないですが、そのように演奏する必然性を確かに感じられますからアリなのでしょう。
当方、名曲喫茶を8年営んでいるにもかかわらず、音楽的専門用語にあまり明るくないので、その箇所を譜面や音楽用語で「ここ」と指摘することはできないのですが、皆さんにも他ピアニストと聴き比べて頂ければ、そのフレーズは瞬時に了解されることと思います。
や、しかし、とくに聴き比べる必要もないかもしれません(あらら)。
というのも、この12番の演奏に関して言えば、グールド氏の演奏を超えて胸に迫ってくるものはこれまでも、この先もないように思われるので。
どう良いのか?と訊かれると、これはもう、聴いて頂くより他ありません。
グレン・グールドは、何かモーツァルトの「神髄」のようなものを確かに掴んでいるように思えてなりません。そんな風に感じるグールドの曲は他にもたくさんさんさんあるのですが……これはまた別の機会に。
次回はA面(ピアノ曲)ラスト、フレデリック・ショパンの「3つの新しい練習曲(B.130)」について書きます。
ピアニストはイタリアが生んだ稀代の天才(稀代の天才ピアニストばかりですが、それでもそう言いたくなる)セルジオ・フィオレンティーノ。これまでほとんど聴いてこなかったこの楽曲について、はたして何か書けるかな……。