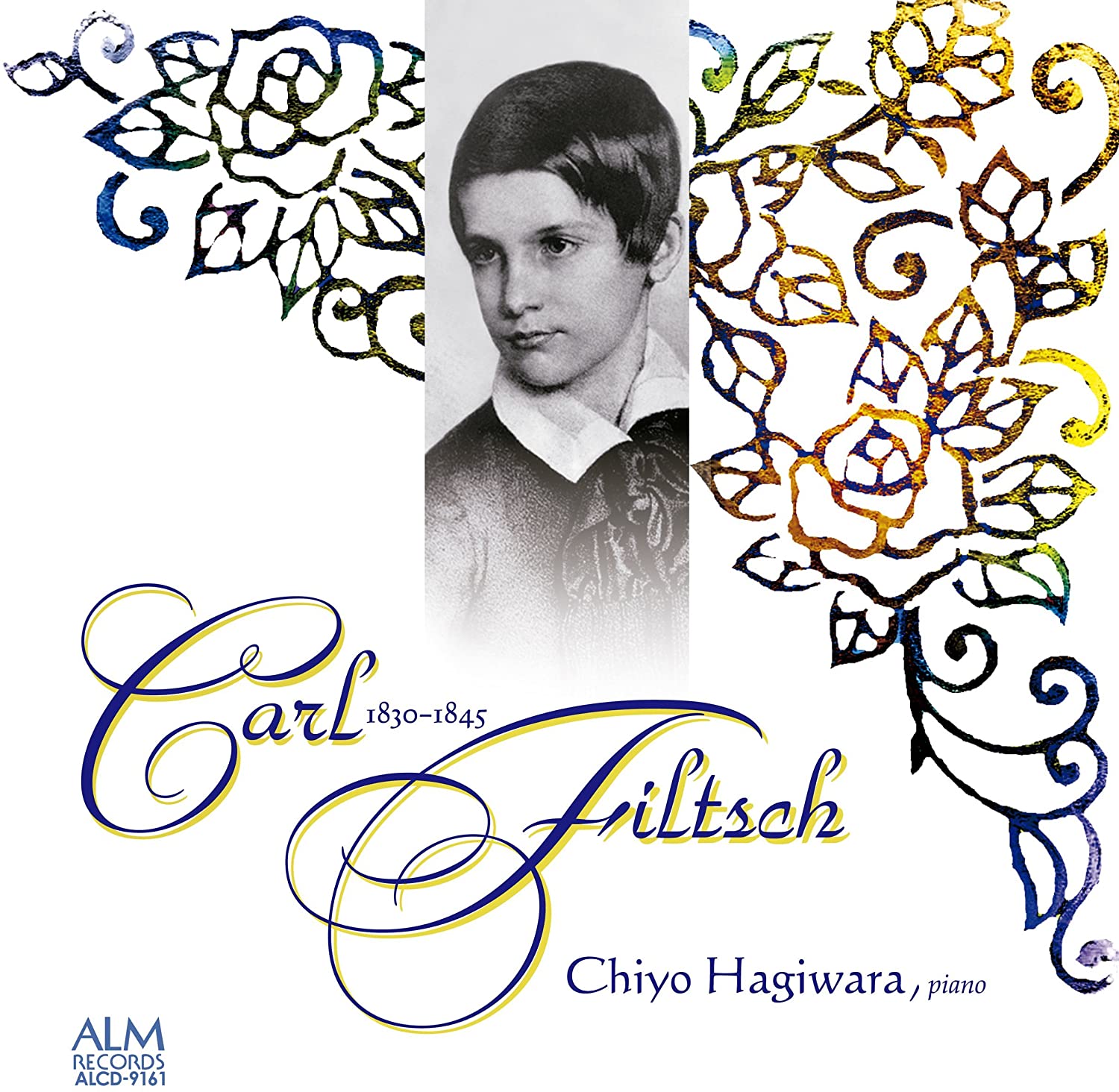シューベルトのピアノソナタ20番(イ長調D.959)は総計たぶん1000回くらい聴いている。や、それは大袈裟か。
でも、たぶん500回は聴いているだろう。ピアニストは、アルフレッド・ブレンデル、あるいはアンドレアス・シュタイアーのフォルテピアノで聴くことが多い。しかし数日前、アドルフ・ブッシュとのデュオで長いこと馴染んできたルドルフ・ゼルキンで聴いてみようと思い立ち、久しぶりに新品のCDを買い求めたのだった。
そうしてこの4日間、心と身体に馴染ませるべく、ずっと聴いている。端的に言って、聴けば聴くほど、「たどたどしい」演奏に感じる。一本気で、慎重で、不器用だ。そういうところが、いかにもゼルキン氏らしい演奏と思える。チャーミングだし、筋が通っているし、ブレンデルのように天才的ではないし、一瞬の煌めきも(今のところ)顕れない。
しかし、僕がこの生涯においてもっとも回数を重ねて聴くであろうピアニストはルドルフ・ゼルキンだろうと(今のところ)強く確信している。次にグレン・グールドが来て、次にワルター・ギーゼキングが来るのだろう。あるいはスヴャ……リヒテル(酔っぱらっているのでフルネームを忘却してしまった)かエドウィン・フィッシャーかもしれない。しかし、それは生涯を俯瞰できる日にならねば判らぬことですが。
そうだのこうだの言っているうちに、ゼルキンのたどたどしいシューベルト20番は今、終演に近づこうとしている。麗しの第四楽章が終わろうとしている。あ″、僕はこの第四楽章を聴きながら、幾度となく君のことを考えたような気がするよ。
君は生涯最後にあたる時期、きっとこの曲を奏でるだろう。それは僕のイメージの中の君でしかないが——君はきっと相当に年老いているだろう。髪の毛はほぼ真っ白で、顔には数多の経験と自分だけで辿り着いた確信と諦念にみちた表情、そして、それに伴った確かな、そして適切な年輪が刻まれていることだろう。でも、マルタ・アルゲリッチにはそれほど似ていない。内田光子さんにもたいして似ていない。ただ、君はただ、ずっとそうであったように——君でしかない。
生来的に、謙虚で引きこもりがちで自己完結的な君のことだから、きっと「誇らしげ」というよりは——ただ爽やかな喜び、そして厳かさにみちみちた、あまり打ち解けなさそうなあの硬い笑みを浮かべつつ、力強く、柔らかく打鍵していることだろう。目を瞑ったまま。その強く瞑想的な打鍵を誰にも止めることはできない。あるいは僕なら止められるのかもしれないが(いや、どうか)、きっと僕はその時、もうこの世にいないような気がする。
このルドルフ・ゼルキンのたどたどしい演奏はそんな計り知り得ない時間のことをたった今、思い起こさせてくれたのだった。